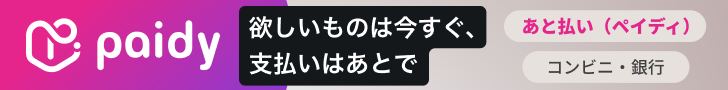栽培レシピ「サヤエンドウ」Vol.3
今月の特集は【サヤエンドウ】です。
玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
サヤエンドウに発生しやすい害虫とその対策ポイント
■ サヤエンドウに付きやすい害虫
サヤエンドウは以下のような害虫の被害を受けやすい作物です:
-
アザミウマ類
-
アブラムシ類
-
エンドウゾウムシ
-
エンドウシンクイガ
-
ハモグリバエ類
-
ヨトウムシ類
-
ハダニ類
これらの害虫が発生すると、サヤが商品価値を失い、生育も大きく妨げられます。
■ 害虫が発生しやすくなる主な原因
サヤエンドウに害虫がつく背景には、以下のような栽培環境の問題があります:
-
有機肥料の過剰使用
-
化成肥料の過剰使用
-
マルチの使用(特に全面マルチ)
-
土壌の水分過多
-
高温期に発生するガス湧き
-
畝まわりの雑草放置
-
排水不良による過湿状態
■ 害虫が発生しやすい時期
以下のような条件が揃うと、害虫の発生リスクが高まります:
-
チッソが分解しやすい高温期
-
春から夏にかけての暑さに向かう時期や残暑が厳しい時期
-
周囲の山野に緑が少ない時期(虫が畑に集中しやすい)
-
ハエやガ類は高温で活発に
-
アブラムシ・ハダニ類は25℃前後で発生しやすい
-
害虫が越冬のために子孫を残す時期(9~10月上旬)
■ 害虫が付きやすい葉の特徴
以下のような葉には特に害虫が集まりやすくなります:
-
根からチッソを過剰に吸収している(チッソのにおいがする)
-
葉肉が薄く、大きく広がっている
-
葉の色が濃い緑色をしている
このような葉は光合成力が弱く、生長力も低いため、根の張りも悪くなります。
また、葉に栄養分が蓄積されやすく、害虫の格好の餌になってしまいます。
■ 害虫被害がもたらす影響
害虫による被害が出ると、以下のような問題が生じます:
-
サヤに食害があり商品化できない不良品が増える
-
生育が悪くなり、収量が低下する
-
出荷時に食害のあるサヤを取り除く手間が大きい
さらに、病害も併発すると消毒や農薬散布の回数が増え、栽培コストも上昇します。
■ 農薬の多用による悪循環
害虫対策で農薬を多用すると、逆に以下のような悪影響が出てきます:
-
葉が弱くなり、生長力が低下
-
葉肉がさらに薄くなり、花芽も減少
-
光合成力が弱くなり、質のよいサヤエンドウが育たない
結果として、手間も増え、費用もかさむ悪循環が生まれます。
まとめ
サヤエンドウは害虫に狙われやすい作物ですが、栽培環境を整えることでリスクを抑えることができます。
とくに大切なのは、以下の3つ:
-
過剰な肥料や水分を避けること
-
排水性をしっかり確保すること
-
チッソの吸収をコントロールし、健全な葉を育てること
薬剤に頼る前に、土づくりと環境管理を徹底することが、健康で高品質なサヤエンドウ栽培の近道です。
こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「サヤエンドウの光合成」についてお届けします!