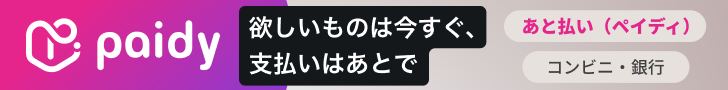栽培レシピ
-
今月の特集は【ショウガ】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 大ショウガの土壌病害と連作障害への対応 大ショウガがかかりやすい病気 大ショウガは、以下のような土壌病害にかかりやすい特徴があります。 腐敗病 立ち枯れ病 白星病 葉枯れ病 イモチ病 モンガレ病 イシュク病 土壌病害の主な原因 病害の多くは、以下のような土壌環境の悪化に起因します。 土中の水分過剰(加湿害) 肥料の過剰投入(=土壌汚染) 耕盤層にたまった老廃物 ロータリー耕による浅耕 植物の根から出る有機酸 連作障害の実態 大ショウガは連作障害が出やすい作物です。とくに問題となるのは、排水不良や肥料の過剰投入による病害の発生です。 いったん病害が出ると、病原菌が土壌に残りやすく、次の作付けでも病気が再発する恐れがあります。これにより、連作が不可能になることも少なくありません。 特に注意すべき時期は、7月中旬~8月下旬の生育旺盛期です。この時期に病害が集中するため、万全な対策が求められます。 ※輪作を行ったとしても、土壌自体が汚染されている場合は根本的な解決にはなりません。 病害対策の基本は「定植前の土づくり」 病害予防の最大のポイントは、定植前の土壌環境の改善です。 カビ由来の病原菌を抑える 土中に十分な酸素を確保する この2つができれば、病害の予防として理想的です。 病害が出るとどうなるか 病気が発生すると、次のような悪影響があります。 生育不良 欠株の増加 品質の低下 収量減少 → 収入減 特に有機肥料はカビの繁殖を助けやすく、化成肥料は過剰投入になりやすいため注意が必要です。 また、収穫されたショウガの貯蔵期間の長さにも影響が出ます。病害のある芋は保存がきかず、商品価値が下がります。 まとめ 大ショウガ栽培においては、排水性の高い土づくりと肥料管理の徹底が、病害予防と連作障害回避のカギです。とくに定植前の耕盤対策や有機酸の排除、土壌の酸素確保がポイントになります。...
-
今月の特集は【ショウガ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 大ショウガの水分管理と灌水のポイント 浅根性ゆえの水分管理の重要性 大ショウガは浅根性植物で、主な根の分布は地表から10〜20cmほどと浅く、一方で細根は70〜80cmまで伸びます。このため、乾燥に非常に弱く、水分の要求量が高い一方で、酸素要求度も高く、通気性のよい土壌が必要です。 適切な水分と酸素を供給するため、スプリンクラーやチューブ灌水などの設備が不可欠であり、地下水位は1〜1.5mが理想とされます。 排水対策の重要性 灌水によって土壌水分が増えると、酸素量が低下し、根にとって悪影響を及ぼすことがあります。そのため、排水対策は極めて重要であり、以下の点に注意します。 明渠排水の設置 地下水への排水ができるような透水性の高い土壌構造をつくる 耕盤(硬盤)を破壊し、深層排水を可能にする構造改善 種球植え付けと初期灌水 植え付け時期:5月初旬 種球が乾かないように、水分補給を丁寧に行うことが重要 植え付け後2〜3日以内に雨が降るのが理想的 → 天気予報を見て、植え付けタイミングを調整するのがよいでしょう 発芽期(6月中旬頃) 植え付けから約40日前後で発芽 発芽後は特に水分要求が高まる時期 土壌を乾燥させないよう、灌水頻度を増やして管理 この時期に**「玄米アミノ酸液肥スーパーカルシウム」**を灌水とともに与えるのが効果的 第一次分球(6月下旬) 芽が出た後は急速に生育し、草丈10〜15cm/葉数2〜3枚に達します 吸肥力が一気に高まる時期 梅雨の時期と重なるため、水分の過不足に要注意 土壌水分が多すぎないか確認しながら灌水 土壌中の滞水や排水不良の見直しも必要 この時期は**水分の量よりも頻度(回数)**が重要です → 10〜20cmの根域を適切に潤す灌水をこまめに行う まとめ:ショウガ栽培の水分管理ポイント 項目 内容 根の性質 浅根性(10〜20cm)だが細根は70〜80cmまで伸びる 灌水設備 スプリンクラーまたはチューブ灌水が必要 地下水位 1〜1.5mが望ましい 排水対策 明渠・耕盤破壊で排水性確保 灌水のコツ...
-
今月の特集は【ショウガ】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ショウガに適した土壌条件 ショウガは浅根性で乾燥に弱く、通気性と排水性を兼ね備えた土壌が必要です。 排水性と保湿性の両立が重要 乾燥に弱いため灌水頻度が多くなりますが、水が滞ると根腐れの原因になります。地下水位は1~1.5mが理想です。 通気性と微生物性の高い土壌が適する 団粒構造で腐植が多く、微生物が豊富な土が望ましく、根の健全な生育を助けます。 明渠排水の設置が効果的 特に大雨のあとは土壌中の酸素が不足しやすく、根の酸欠を防ぐためにも、明渠による排水対策が必要です。 土づくりと耕うん深さ 作土層は30〜40cmが目安 深耕により酸素量が確保され、分球と肥大が進んで収量が増加します。 →プラソイラを使用した深耕作業を推奨します。 土壌pHの管理 適正pHは5.5〜6.0 ショウガは比較的酸性に強いものの、pH5.5を下回ると生育不良になります。 乳酸菌もみがらぼかしと一緒に有機石灰を施用 定植前のpH調整は以下を目安に行います: 土壌pH 有機石灰の投入量(10aあたり) 5.0〜5.3 300kg 5.3〜5.6 200kg 5.6〜5.9 100kg 6.0以上 50kg ※有機石灰は殺菌済みのものを使用し、pH値は事前に土壌分析で必ず確認しましょう。※この調整を行えば、苦土石灰などの施用は不要です。 栽植設計と定植密度 高畝にして栽植 根の健全な呼吸のためにも、高畝栽培が基本です。 栽植設計 - 株間:30cm - 畝幅:60cm - 10aあたりの定植本数:約5,400株 肥料設計(乳酸菌もみがらぼかし使用) 乳酸菌もみがらぼかしのみで肥培管理が可能です。化学肥料は不要です。 基肥:600kg(チッソ換算18kg) 追肥: - 100kg × 2回 - 200kg × 1回(合計3回) → チッソ換算12kg(上記はすべてもみがらぼかし中に含まれる量です) まとめ...
-
今月の特集は【シュンギク】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部お届けします。 光合成の力で品質アップ! シュンギクの生長と光の関係 シュンギクは好光性植物で、光にとても敏感な性質を持っています。光合成によって栄養素(炭水化物)を自ら作り出し、全体の生長の80%以上を支えるといわれています。 光合成が活発になると糖度が上がり、品質も大きく向上します。生育もスムーズで、収量や味の面でも優位性があります。 草丈10cmから本格的な生長ステージへ 光合成が本格化するタイミング シュンギクは草丈10cmを超えると、生長が最も活発になります。この時期、葉で作られた栄養が根に送られることで、根の張りも良くなり、さらに生長が加速していきます。 このタイミングに合わせて、玄米アミノ酸酵素液を葉面散布することで、期待通りの生育をサポートできます。 葉が水分を調整する 根と葉の役割の違い シュンギクの根は構造が単純で水分調整の機能はありません。 一方、葉は構造が複雑で水分をコントロールする機能を持っています。つまり、葉が元気であること=全体の生育の鍵となるのです。 光合成しやすい「良い葉」とは? 活発な光合成が行える葉の特徴は以下の通りです: 葉肉が厚い 色がやや淡い 大きく広がりすぎない チッソ過多でない 葉脈が立っており、産毛が多い このような葉は、病害虫にも強く、全体の健康を保つ上で理想的です。 玄米アミノ酸酵素液で光合成を促進 500倍希釈液を、10アールあたり300L散布することで、次のような効果が期待できます: 光合成が促進される 生長スピードがアップ 葉が厚くなり、甘味が増す 病害虫の予防にも効果的 光合成で健全な環境に みどりの放線菌(病害対策) ニーム酵素液(害虫対策) これらを光合成と併用することで、病害虫の被害が少ない環境をつくることができます。 トラブル発生時:随時使用 予防目的:週1回の使用が推奨 みどりの放線菌:200gあたり100Lで使用を検討 光合成に「やりすぎ」はない! 肥料や農薬には「過剰障害」がつきものですが、光合成だけは“やりすぎによる害”がありません。毎日でも実施できますが、作業の都合で回数を減らしているだけで、回数を増やすほど生長が早まり、旨味もアップします。 つまり、植物が必要とする栄養素を、自ら作り出せる環境こそが理想なのです。 まとめ シュンギクの栽培では、光合成の促進が品質と生長のカギを握ります。特に、草丈10cm以降のタイミングに注目し、玄米アミノ酸酵素液を葉面散布することで、葉・根・全体の成長が加速します。 また、病害虫の予防も**微生物や酵素を活用した“光合成中心の管理”**によって可能になります。光合成には過剰害がなく、必要な栄養素を必要な時に生み出せるため、理想的な栽培サイクルをつくる要となります。...
-
今月の特集は【シュンギク】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 シュンギクの病害とその原因 かかりやすい病気 黒斑病、さび病、炭疽病、葉枯病、べと病、モザイク病 発生の主な原因 湿害・雨への弱さ:湿気や降雨が多いと病原菌が活性化しやすくなる 肥料過多:過剰な養分がカビの発生を考える ※病害が出てからの対処は難しいため、事前の土づくりが決定的に重要です。 シュンギクの生理障害と土壌の影響 よく見られる障害 チップバーン、芯枯れ症 マンガンの不足・過剰 カルシウム、ホウ素、銅、亜鉛、マグネシウムなどの微量要素の欠乏 発生原因 土壌のバランス崩壊や地力の低下 湿害による酸素不足 ※土壌環境が悪いままだと、これらの障害は毎年繰り返し発生します。 連作障害とその心理 主な原因 土壌汚染(有機酸や病原菌の残留) 土壌消毒の繰り返し → 地力の低下 マルチによる光遮断 → 嫌気性病原菌の繁殖 ※連作障害は、知らずのうちに生産者自身がいるケースもあります。 解決策: 乳酸菌もみがらぼかしの活用 微生物の力で土壌を浄化 酸素が豊富な健全な土壌環境を形成する 連作障害の発生リスクが軽減 土壌病害の原因と対策 主な原因 過湿・加湿害 肥料過剰(塩害) 耕盤層の老廃物 浅耕(土が十分に混ざらない) 植物が排出する有機酸の一時 病害が出やすい時期...