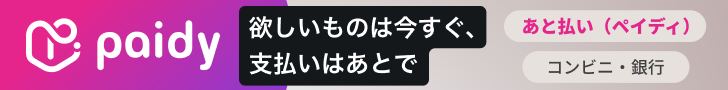栽培レシピ「サヤインゲン」Vol.4
今月の特集は【サヤインゲン】です。
玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
サヤインゲンと光合成の関係
■ 光合成は栄養と品質を左右する
植物は、葉の光合成によって水と二酸化炭素から炭水化物(糖)を作り出し、それを栄養として成長します。
この栄養は生長に必要なエネルギーの8割以上を占めており、糖度の向上にもつながります。
とくに**着さや後(実がついてから)**の光合成は非常に重要で、
・糖度が大幅にアップ
・サヤのツヤも美しくなり
・品質も収量も向上します。
※「つるあり種」は光合成量が増えやすく、収量が大きく伸びる傾向にあります。
■ サヤインゲンは“光合成に結果が出やすい作物”
-
葉数が増えるほど光合成量が増し、生育スピードも加速
-
光合成が活発なほど糖分が高まり、味にコクが出る
-
質の良いサヤが収穫できるようになる
■ 葉と水分コントロールの関係
-
根は構造が単純で、水分を調整する機能はありません
-
一方で葉は水分調整機能を持つ複雑な構造になっています
光合成を活発にする「良い葉」の特徴:
-
葉肉が厚い
-
葉色が淡く、過度に広がっていない
-
チッソ過多ではない
-
葉脈が立っており、産毛が多い
このような葉は、病害虫の予防にも効果的です。
■ 栄養を蓄え、実を美しく仕上げる
サヤインゲンは光合成によって栄養を蓄積し、サヤも肥大。
着さや後に葉面散布を行うと、花芽が増え、収量もアップします。
◎ 玄米アミノ酸酵素液:500倍希釈で葉面散布
◎ みどりの放線菌(病害対策):200gを100Lに
◎ ニーム酵素液(害虫対策):週1回を目安に予防
■ 光合成は「やりすぎ」がない唯一の要素
通常の農業では、「過剰」はトラブルの原因になりますが、
光合成だけは、どれだけ促進しても害が出ません。
・毎日行っても問題なし
・作業負担の都合で減らすケースが多いが、回数が多いほど甘味・旨味が増す
まとめ
サヤインゲンは、光合成の効果がはっきりと現れる作物です。
適切な栽培管理と葉面散布により、
・糖度が高く、
・ツヤのあるサヤ
・収量も増加し、
・病害虫の予防にもつながります。
とくに着さや後の管理が品質を左右します。
**“光合成の力を最大限に活かすこと”**が、美味しいサヤインゲンづくりの近道です。
こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「サヤエンドウの土壌作り」についてお届けします!