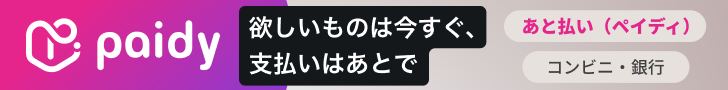栽培レシピ「ショウガ」Vol.3
今月の特集は【ショウガ】です。
玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
大ショウガの土壌病害と連作障害への対応
大ショウガがかかりやすい病気
大ショウガは、以下のような土壌病害にかかりやすい特徴があります。
-
腐敗病
-
立ち枯れ病
-
白星病
-
葉枯れ病
-
イモチ病
-
モンガレ病
-
イシュク病
土壌病害の主な原因
病害の多くは、以下のような土壌環境の悪化に起因します。
-
土中の水分過剰(加湿害)
-
肥料の過剰投入(=土壌汚染)
-
耕盤層にたまった老廃物
-
ロータリー耕による浅耕
-
植物の根から出る有機酸
連作障害の実態
大ショウガは連作障害が出やすい作物です。
とくに問題となるのは、排水不良や肥料の過剰投入による病害の発生です。
いったん病害が出ると、病原菌が土壌に残りやすく、次の作付けでも病気が再発する恐れがあります。これにより、連作が不可能になることも少なくありません。
特に注意すべき時期は、7月中旬~8月下旬の生育旺盛期です。この時期に病害が集中するため、万全な対策が求められます。
※輪作を行ったとしても、土壌自体が汚染されている場合は根本的な解決にはなりません。
病害対策の基本は「定植前の土づくり」
病害予防の最大のポイントは、定植前の土壌環境の改善です。
-
カビ由来の病原菌を抑える
-
土中に十分な酸素を確保する
この2つができれば、病害の予防として理想的です。
病害が出るとどうなるか
病気が発生すると、次のような悪影響があります。
-
生育不良
-
欠株の増加
-
品質の低下
-
収量減少 → 収入減
特に有機肥料はカビの繁殖を助けやすく、化成肥料は過剰投入になりやすいため注意が必要です。
また、収穫されたショウガの貯蔵期間の長さにも影響が出ます。病害のある芋は保存がきかず、商品価値が下がります。
まとめ
大ショウガ栽培においては、排水性の高い土づくりと肥料管理の徹底が、病害予防と連作障害回避のカギです。
とくに定植前の耕盤対策や有機酸の排除、土壌の酸素確保がポイントになります。
病害を防ぐことで、品質の高いショウガの安定生産と収入の確保につながります。土づくりを軽視せず、計画的に整備していきましょう。
続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「ショウガの光合成」についてお届けします!