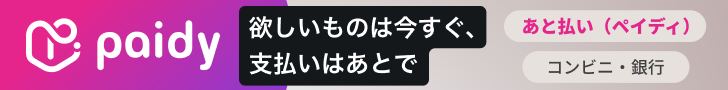栽培レシピ「コマツナ」Vol.1
今月の特集は【コマツナ】です。
玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
コマツナ栽培における土壌管理と肥料のポイント
コマツナ栽培の特徴
-
作付け回数が多く、残った肥料(残肥)が土壌に蓄積しやすい
-
浅根性のため、根が浅く、酸素を多く必要とする
-
生育には、排水性が良く、団粒構造が整った微生物豊富な土壌が最適
-
土壌環境が良いほど、根コブ病や萎黄病などの病害も少なくなる
-
稲作からの転作でも、土壌条件を整えれば問題なく栽培可能
-
排水が良く、適度に水持ちのある土壌が理想
肥料の使いすぎに注意
-
有機・化成肥料を多く投入しすぎると、土は徐々に硬くなり排水性や保水力が低下
-
年に何度も作付けをするため、そのたびに肥料や石灰を過剰投入しやすい
-
欠乏ではなく過剰症が原因で生育不良になることが多く、土壌の酸性化や病害発生にもつながる
明渠排水の整備
-
大雨対策として明渠排水は必須
-
土壌が雨で酸素不足にならないようにし、酸素を好むコマツナの健全な生育を支える
プラソイラによる深耕
-
2~3回の深耕を推奨
-
土壌に酸素を含ませることで、残肥の分解が進み、根の伸びも良くなる
-
排水性・通気性を向上させるために非常に重要な作業
土壌のpHと吸肥力
-
適正pHは6.0〜6.5
-
pHが適正になることで微生物が活発に働き、吸肥力もアップ
-
コマツナは後半の吸肥力が特に高いため、微生物とチッソの働きが生育に大きく貢献する
乳酸菌もみがらぼかしの活用
-
基肥として10アールあたり400kgを投入
-
チッソ量(基肥中)=約12kg
-
連続作付けするほど、土壌が団粒化し、微生物性が高まる
-
その結果、病害も大きく減少し、健全な土壌環境が維持できる
コマツナの栽培では、**「土づくりがすべて」**と言えるほど、事前の土壌管理が成果に直結します。適切な排水、pH、肥料のバランスを保ち、微生物の力を活かして、健康でおいしいコマツナを育てましょう。
こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「コマツナの病害」についてお届けします!