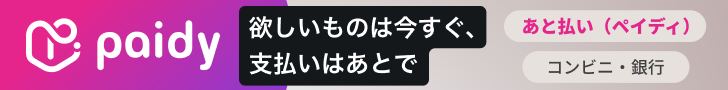栽培レシピ「サヤインゲン」Vol.1
今月の特集は【サヤインゲン】です。
玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
サヤインゲン栽培に適した土づくりのポイント
■ 土壌づくりは「2回」行う
サヤインゲンは酸素要求度が非常に高い作物です。そのため、土壌をふかふかの団粒構造に整える必要があります。
-
前年の秋と、作付前の2回に
**「乳酸菌もみがらぼかし」**を投入しておくことが重要です。 -
作付前の施肥は、窒素量を8〜10kg/10アールに抑えることで、つるボケを防ぎます。
■ 明渠排水の整備
大雨などの際に、土壌が酸素不足に陥らないよう、明渠排水(排水溝)の整備を行いましょう。
-
過剰な水分(過湿)は、生理障害や病害の主な原因になります。
-
特にサヤインゲンは、過湿に非常に弱く、
連作や土壌病害にも敏感な作物です。
→ 排水性の確保は栽培成功のカギです。
■ プラソイラでの深耕
酸素を多く含む土壌環境を整えるために、
プラソイラを用いて耕盤層・硬盤層を破壊し、通気性と排水性を向上させます。
-
作土層は30cm以上を確保
-
稲作転作地(元・水田)では特に重要です
→ 排水が悪いと、病気が出やすくなります。
■ 土壌の基本条件
-
pH:6.0〜6.5
-
作土層の深さ:50〜60cm
-
基肥として、乳酸菌もみがらぼかしを10アールあたり400kg投入
-
窒素量としては約12kg相当
-
→ 団粒構造をつくり、微生物を増やして地力を高める効果があります。
■ 土壌改良のタイミングと方法
作付前年の秋に
-
乳酸菌もみがらぼかしを300kg×2回 または 600kg×1回施用
-
同時にプラソイラで深耕を実施
→ これにより、土がふかふかの団粒構造となり、根張りも良くなります。
■ pH調整と有機石灰の施用量目安
乳酸菌もみがらぼかしを施す際に、有機石灰(殺菌済み)も同時にすき込むことで、pHを適正に保ちます。
| 土壌pH | 有機石灰の施用量(10アールあたり) |
|---|---|
| 5.0~5.3 | 300kg |
| 5.3~5.6 | 200kg |
| 5.6~5.9 | 100kg |
| 6.0以上 | 50kg |
まとめ
サヤインゲンの健全な生育には、酸素を含んだふかふかの土壌と、適切な水分・pH管理が欠かせません。
「前年の土づくり+作付前の仕込み」で、連作障害や病害虫リスクを大きく減らすことができます。
こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「サヤインゲンの水分の与え方」についてお届けします!