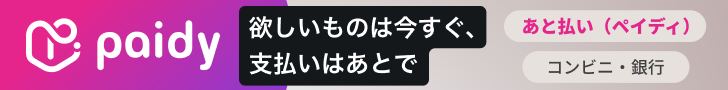栽培レシピ「シュンギク」Vol.3
今月の特集は【シュンギク】です。
玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。
シュンギクの病害とその原因
かかりやすい病気
-
黒斑病、さび病、炭疽病、葉枯病、べと病、モザイク病
発生の主な原因
-
湿害・雨への弱さ:湿気や降雨が多いと病原菌が活性化しやすくなる
-
肥料過多:過剰な養分がカビの発生を考える
※病害が出てからの対処は難しいため、事前の土づくりが決定的に重要です。
シュンギクの生理障害と土壌の影響
よく見られる障害
-
チップバーン、芯枯れ症
-
マンガンの不足・過剰
-
カルシウム、ホウ素、銅、亜鉛、マグネシウムなどの微量要素の欠乏
発生原因
-
土壌のバランス崩壊や地力の低下
-
湿害による酸素不足
※土壌環境が悪いままだと、これらの障害は毎年繰り返し発生します。
連作障害とその心理
主な原因
-
土壌汚染(有機酸や病原菌の残留)
-
土壌消毒の繰り返し → 地力の低下
-
マルチによる光遮断 → 嫌気性病原菌の繁殖
※連作障害は、知らずのうちに生産者自身がいるケースもあります。
解決策: 乳酸菌もみがらぼかしの活用
-
微生物の力で土壌を浄化
-
酸素が豊富な健全な土壌環境を形成する
-
連作障害の発生リスクが軽減
土壌病害の原因と対策
主な原因
-
過湿・加湿害
-
肥料過剰(塩害)
-
耕盤層の老廃物
-
浅耕(土が十分に混ざらない)
-
植物が排出する有機酸の一時
病害が出やすい時期
-
**高温多湿期(春〜夏)**に多い
-
**寒期(秋〜冬)**には比較的出にくい
対策の基本
-
定植前の土づくりが最も重要
-
カビの原因を取り除き、土壌中の酸素量を十分に確保することで病害を予防する
まとめ
シュンギクは湿害と肥料過多に非常に敏感な作品です。病害や生理障害、連作障害のほとんどは土壌環境の悪化が原因であり、発生後の対処では根本解決になりません。そのため
、栽培前の健全な土づくりがすべての基本です。
特に「乳酸菌もみがらぼかし」を置くことで、微生物の力による自然な土壌改善が期待でき、カビや病害の発生を集中することができます。連作障害の防止や収量安定にもつながるため、長期的な視点での土壌管理がシュンギク栽培の成否を分けます。
続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。
次回は「ジャガイモの光合成」についてお届けします!