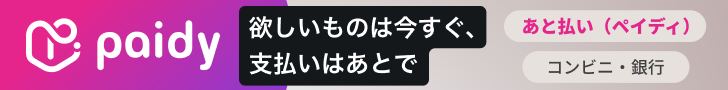栽培レシピ
-
今月の特集は【ジャガイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ジャガイモ栽培の基本:ほ場選定と土づくり ■ 1. ほ場選定のポイント 排水性が良い土地を選ぶことが最重要 ジャガイモは排水不良による土壌病害(特にカビ病)に弱いため、排水対策が不可欠です。 有機肥料を過剰に与えると病害が出やすくなるため、適量を守ることが大切です。 同一ほ場での連作は避けましょう(連作障害の原因になります)。 明渠(排水溝)を設けて大雨時の水はけを確保し、土壌の酸素不足を防ぎます。 ■ 2. 土づくりと深耕 作土層は30cm以上が理想 深耕により酸素の供給量を確保し、でんぷん含量の高い大きな芋の収穫が期待できます。 プラソイラなどを用いて深耕し、排水性をさらに向上させることが重要です。 pHは6.0前後が適正 ジャガイモはやや酸性を好む作物。pH6前後がベスト。 稲作からの転作でも栽培可能ですが、排水性の確保が前提となります。 肥料設計:乳酸菌もみがらぼかしの活用 ■ 3. 肥料の施用量とタイミング(10アールあたり) 基肥:乳酸菌もみがらぼかし500kg 追肥:100kg(必要に応じて中耕と同時に1回) ぼかしに含まれるチッソ量(参考値): 基肥:15kg 追肥:3kg 作型や品種によってチッソの最適量は変わりますが、基本は基肥500kgで十分に対応可能です。 追肥は原則不要ですが、生育状況を見ながら1回程度行うと良いです。 ジャガイモには土壌微生物由来のチッソが最も適しており、収量を上げるには微生物活性と土壌の酸素量が鍵となります。 ■ 4. pH調整の方法(有機石灰) 乳酸菌もみがらぼかしの投入時に、殺菌済みの有機石灰を一緒にすき込み、pH調整を行います。 土壌pH 有機石灰施用量(10アールあたり) 5.0~5.3 300kg 5.3~5.6...
-
今月の特集は【サヤエンドウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤエンドウは“光合成”で収量アップ! ■ 植物の生長は光合成から サヤエンドウをはじめ、植物は葉で光を受けて「光合成」を行い、水と二酸化炭素(CO₂)から炭水化物をつくり出します。この炭水化物は、植物全体の生長に使われる栄養の80%以上を占める重要なエネルギー源です。 光合成がしっかり行われることで、 糖度が上がって品質が良くなる 花芽が増える 樹勢(元気さ)を保てる 開花から収穫までの期間が短縮され、収量もアップ といった効果が期待できます。 ■ 葉が多いほど光合成量が増える 植物が育って葉の枚数が増えるほど、光合成の量も増加。つまり、葉を健康に保つことが、生長促進と高品質なサヤ作りのカギになります。 光合成の活発なサヤエンドウは、 生長が良く 糖度が高くなり 見た目にもツヤのある美しいサヤに仕上がります。 ■ 水分コントロールと「葉の状態」が重要 根は構造が単純で、自ら水分の調整はできません。水分コントロールの役割は、葉が担っています。 光合成が活発に行われる理想的な葉の特徴は: 葉肉が厚く、色が淡い 大きく広がらず、チッソ過多でない 葉脈が立ち、産毛が多い こうした葉は、病害虫にも強く、健康的なサヤエンドウが育ちます。 ■ 葉面散布で光合成をサポート 「玄米アミノ酸酵素液」を葉にスプレーすることで、 葉の質が良くなり 花芽が増えて 収量が大幅にアップします。 さらに、 みどりの放線菌(病害予防) ニーム酵素液(害虫忌避)の活用もおすすめです。 トラブル対応はもちろん、**予防的には週1回(着さや後)**の散布が理想。目安は「みどりの放線菌200gを水100Lに溶かして」使用します。 ■ 光合成に“やりすぎ”はない 農業では「肥料や水分のやりすぎ」がトラブルの原因になりますが、光合成に“過剰”はありません。毎日でも問題なく、回数が多いほど生長も早く、旨味も増します。 サヤエンドウは、特に光合成の効果が出やすい作物。葉の管理とサポートをしっかり行うことで、花芽の数も増え、収穫量もグッと向上します。...
-
今月の特集は【サヤエンドウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤエンドウに発生しやすい害虫とその対策ポイント ■ サヤエンドウに付きやすい害虫 サヤエンドウは以下のような害虫の被害を受けやすい作物です: アザミウマ類 アブラムシ類 エンドウゾウムシ エンドウシンクイガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ハダニ類 これらの害虫が発生すると、サヤが商品価値を失い、生育も大きく妨げられます。 ■ 害虫が発生しやすくなる主な原因 サヤエンドウに害虫がつく背景には、以下のような栽培環境の問題があります: 有機肥料の過剰使用 化成肥料の過剰使用 マルチの使用(特に全面マルチ) 土壌の水分過多 高温期に発生するガス湧き 畝まわりの雑草放置 排水不良による過湿状態 ■ 害虫が発生しやすい時期 以下のような条件が揃うと、害虫の発生リスクが高まります: チッソが分解しやすい高温期 春から夏にかけての暑さに向かう時期や残暑が厳しい時期 周囲の山野に緑が少ない時期(虫が畑に集中しやすい) ハエやガ類は高温で活発に アブラムシ・ハダニ類は25℃前後で発生しやすい 害虫が越冬のために子孫を残す時期(9~10月上旬) ■ 害虫が付きやすい葉の特徴 以下のような葉には特に害虫が集まりやすくなります: 根からチッソを過剰に吸収している(チッソのにおいがする) 葉肉が薄く、大きく広がっている 葉の色が濃い緑色をしている このような葉は光合成力が弱く、生長力も低いため、根の張りも悪くなります。また、葉に栄養分が蓄積されやすく、害虫の格好の餌になってしまいます。 ■...
-
今月の特集は【サヤエンドウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤエンドウの好む土壌水分と管理のポイント ■ 透水性の高い土壌が基本 サヤエンドウには砂壌土〜壌土のような、透水性に優れた土壌が適しています。特に注意したいのは「排水性」で、栽培開始前にしっかりと排水設計をしておく必要があります。 サヤエンドウは根が深く張るため、1m以上の透水層が必要です。水が溜まりやすい場所では停滞水が発生しやすく、病害や品質低下の原因となるため、水はけのよい土づくりが重要です。 ■ 停滞水による影響 土壌に水が滞ると、以下のような問題が発生します: 病害が出やすくなる 樹勢が落ち、分枝数が減る サヤの曲がりが多くなる 品質・収量の低下につながる こうしたリスクを避けるには、過湿に注意しながら水分を管理することが不可欠です。 ■ 初期生育では「酸素」が重要 サヤエンドウの根は主根型で、1m以上深く伸びる構造をしています。側根や毛細根が少ないため、水分よりも酸素を必要とする作物です。 特に初期生育期では、水を与えすぎると根の発育が妨げられるため、注意が必要です。 ■ 分枝数の増減に関わる要素 分枝数は、水分の量ではなく、土壌中の酸素量によって左右されます。 水分が多すぎる 頻繁に水を与えすぎる これらの条件では、分枝が少なくなり、生育も悪くなります。直根がよく伸びるということは、それだけ吸水力が高いことを意味します。よって、水分や肥料のやり過ぎは避け、必要最小限に抑えることが分枝数を増やすポイントです。 ■ つるぼけを防ぐには サヤエンドウはもともと徒長しやすく、「つるぼけ」になりやすい特性を持っています。つるぼけの主な原因は2つ: 水分の与え過ぎ 肥料のやり過ぎ このような状態になると、過繁茂になってサヤが不良になりやすく、収量の低下につながります。 まとめ サヤエンドウは、水よりも酸素を必要とする深根性の作物です。健やかな生育と分枝数の確保には、以下の点が大切です: 栽培前から排水性の高い土壌を整える 過湿を避け、水分の与えすぎに注意する 肥料も控えめにし、徒長やつるぼけを防ぐ これらを意識した水分管理により、品質の良いサヤエンドウを育てることができます。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「サヤエンドウの病害・または害虫」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【サヤエンドウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤエンドウの栽培管理と土づくりのポイント ■ サヤエンドウは酸素を多く必要とする作物 サヤエンドウは直根が1メートル以上伸びる深根性の作物です。特に土壌中の酸素要求量が25%以上と高く、酸素の多い土壌でこそよく育ちます。 酸素量を確保するには、微生物の働きを活かした土づくりが重要です。 ■ 微生物を活かした土づくり 前年の秋に、・乳酸菌もみがらぼかしを10アールあたり600kg・プラソイラ(深耕機)で耕盤層を壊しながら投入 これにより、土壌が団粒化し、酸素を多く含むふかふかの土壌になります。酸素が多い土では、根の分枝も増え、生育が良くなります。 ■ 排水性の確保が重要 サヤエンドウは過湿に弱く、生理障害や病害の原因になります。特に大雨の際、土壌が酸素欠乏にならないように、**明渠排水(溝をつける)**が必須です。 加えて、・プラソイラによる深耕で硬盤層・耕盤層を破壊・作土層は60cm以上確保・停滞水をつくらない排水設計が重要です。 ■ 土壌条件の整備 土壌pHは6.5が理想(酸性に弱い) 作土層の深さは60cm以上 根粒菌の働きを活かすにはpH6.0~6.5が必要 <pH調整の目安(有機石灰を使用)> ※施用は種まきの1か月前までに済ませておく pH5.0~5.3 → 300kg pH5.3~5.6 → 200kg pH5.6~5.9 → 100kg pH6.0~ → 50kg※殺菌済みの有機石灰が望ましい ■ 肥料設計と乳酸菌もみがらぼかしの活用 乳酸菌もみがらぼかしは、土壌を団粒化し、微生物を増やす効果があります。これにより、地力が高まり、健康なサヤエンドウの育成に貢献します。 <投入量の目安> 基肥:10アールあたり400kg(スナップエンドウの場合は600kg) 追肥:10アールあたり100kg ×...