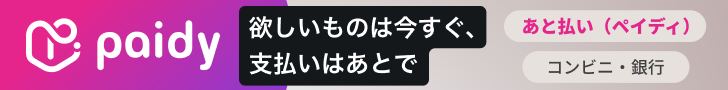栽培レシピ
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツの害虫対策について 河北小松菜はアブラナ科に属し、以下のような害虫が付きやすいです ・コナガ・アブラムシ・キスジノミハムシ・アザミウマ類アブラナ科の植物はチッソ過多の土壌に対して特に敏感で、これが害虫の発生を助長します。チッソ過剰は、葉が薄く、広がりやすくなり、光合成力や生長力が弱くなります。 害虫が発生しやすい時期 チッソが分解しやすい高温期や、周囲の植物が少ない秋~冬~春です。特にアブラムシが発生しやすくなります。害虫が付きやすい葉の特徴として、大量のチッソを根から吸収している葉は、葉肉が薄く、大きく広がり、濃緑色をしています。こうした葉は光合成力や生長力が弱く、根の張りも良くありません。 害虫の発生原因 肥料過剰、水分過剰、排水不良です。 害虫による影響 商品価値のない不良品の発生、生長不良、大株にならないこと、収量の減少などが挙げられます。 害虫対策 まずチッソ過多の土壌にしないことが重要です。また、過剰加湿による根の水分異常吸収に注意することも必要です。これらの対策を講じることで、河北小松菜の健全な生長を促し、収量を安定させることができます。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「コマツナの光合成」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツの水分の与え方について 玄米アミノ酸酵素液での処理 種を500倍希釈した玄米アミノ酸酵素液に3時間浸します。小松菜の種は白菜に近く、柔らかくて発芽しやすいため、この処理が効果的です。浸した種は風通しの良い場所で陰干しし、水分を飛ばします。 播種条件 播種時には種を乾燥させず、発芽までしっかりと水分を与えます。10アール当たり2~3トンの水が必要です。発芽適温は17~25℃で、これを守ることで発芽が良くなります。 天然ミネラルと放線菌の使用 発芽を促進するために、天然ミネラル鉱石30kgとみどりの放線菌2kgを混合し、種まきの際に筋に投入します。これにより悪玉細菌の発生を予防し、発芽率を高めることができます。目標発芽率は98%です。 覆土の方法 播種後の覆土は種の厚さの3倍が基本ですが、厚くかけすぎないように注意します。 播種後の水分管理 播種後、玄米アミノ酸酵素液を1000倍希釈し、10アール当たり2~3トンの水を与えます。土が乾燥しないようにし、種には充分な水分を含ませることで発芽しやすくなります。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「コマツナの害虫」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツナの土壌作りについて ほ場の選定 小松菜の栽培には、排水が良く水持ちが良い団粒の土壌が適しています。明渠排水を行い、大雨時の降雨対策をすることで、土壌が雨で酸素欠乏にならないようにしましょう。 作土層の準備 作土層は30~40㎝の深さが理想で、主根が根を張る範囲を確保します。深耕するためにはロータリーを使用し、特にプラソイラでの深耕がおすすめです。 土壌のpH調整 土壌の適正pHは6.0~6.5で、酸性にも強いですがpH5.5以下は避けるべきです。pHが低すぎるとトラブルが多発します。 畝立てと肥料の投入 畝立ては株間15cm、条間15cmで行います。基肥として10アール当たり300~400kgの乳酸菌もみがらぼかしを投入し、追肥する場合は300kg、追肥しない場合は基肥として450kgを使用します。チッソ量は10アール当たり9kg~13.5kgを目安とし、追肥量は10アール当たり100kgです。 pH調整方法 事前調査: 土壌のpHを事前に調べましょう。乳酸菌もみがらぼかし投入時: 有機石灰を同時にすき込んでください。pH5.0~5.3の場合: 有機石灰300kgpH5.3~5.6の場合: 有機石灰200kgpH5.6~5.9の場合: 有機石灰100kg(有機石灰は殺菌したものを使用するのが良いでしょう) こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「コマツナの水分の与え方」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【エダマメ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 エダマメの光合成と栽培管理 エダマメは高温性作物で、葉の光合成によって栄養を作り、生長します。水とCO2を使って炭水化物を生成し、この栄養が成長の80%以上を占めることで、糖度が大幅にアップし、品質が向上します。高温性作物ほど光合成は活発になり、着サヤも多くなり、子実も肥大して糖度が高くなります。 害光合成と葉の役割 エダマメの光合成は、植物体が成長するほど、また葉数が多くなるほど活発になります。光合成が進むことで、実がプックリと肥大し、糖度も高くなります。これにより、未熟でも成長が早くなり、質の良いエダマメが育ちます。 水分コントロール エダマメの根の構造は単純で水分コントロールはできませんが、葉の構造は複雑で水分コントロール機能を持っています。光合成が活発にできる「葉」は、葉肉が厚く、色が淡く、大きく広がらないものが理想です。チッソ過多でない葉、葉脈が立ち、産毛が多い葉は、病虫害の防止にも役立ちます。 光合成による生育促進 エダマメは光合成によって肥大し、栄養が蓄えられます。これにより、着サヤもツヤが出て美しくなります。玄米アミノ酸酵素液の葉面散布を行うと、大粒の子実(豆)になります。光合成による病害・害虫予防として、みどりの放線菌は病害、ニーム酵素液は害虫対策に有効です。 光合成の重要性 商光合成に過剰な害はありません。農業では「過多」が障害の原因になることが多いですが、光合成については毎日行っても問題ありません。仕事量の関係で回数を少なくしていますが、回数が多いほど成長も早く、旨味も増します。エダマメは特に光合成による結果が顕著に出る作物で、大粒になり、糖分の高い旨味とコクが得られます。 実践的なアドバイス 予防的な対策として、みどりの放線菌200gを100Lに混ぜて週1回散布すると効果的です。玄米アミノ酸酵素液を葉面散布すると、エダマメの質が向上します。光合成を活発にするために、葉の管理を徹底しましょう。これらのポイントを実践することで、エダマメの栽培が成功し、質の高い収穫が期待できます。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。来月は「コマツナ」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【エダマメ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 エダマメの根系と土壌管理 エダマメに付きやすい害虫とその原因 エダマメにはアブラ虫類、カメ虫類、キタバコガ、ダイズクキタマバエ、ダイズシストセン虫、タネバエ、ハスモンヨトウ、ヒメコガネ、マメシンクイガ、ハダニ類、オンブバッタ、フタスジヒメハムシ、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、ダイズサヤムシガなどの害虫が付きやすいです。 害虫が発生しやすい原因は以下の通りです ・有機肥料や化成肥料の過剰使用・マルチ(特に前面マルチ)の使用・土壌水分の過剰・高温期のガス湧き・周囲の雑草・排水不良 害虫は特にチッソが分解しやすい高温期や、暑さが厳しい時期に発生しやすく、周囲の山野に植物が少ない時にも多くなります。ハエやガ類は高温期に、アブラ虫やダニ類は25℃前後で発生しやすいです。また、害虫が子孫を残す越冬期(9~10月上旬)にも注意が必要です。 害虫が付きやすい葉とその影響 害虫が付きやすい葉は、チッソを根から大量に吸収しており、チッソの香りがする葉です。こうした葉は、葉肉が薄く、大きく広がり、濃緑色をしています。しかし、これらの葉は光合成力も生長力も弱く、根の張りも良くありません。土壌の養分が葉に蓄えられるため、エダマメの葉は薄くなり、害虫に食べられやすい状態になります。 害虫による食害の影響は以下の通りです ・商品化できない不良品が増える・生長が良くない・出荷時に食害を受けた子実(サヤ)を取り除く手間がかかる・病害と害虫の発生で消毒の回数が増える・農薬の使用回数が増えると葉が弱くなり、生長が悪くなる 特に葉肉が薄くなると、マメの実入りも悪くなり、光合成力も低下するため、良質のエダマメができなくなります。これにより、手間も費用も高くなります。これらの点を踏まえて、エダマメの栽培管理を見直し、害虫被害を減らすことで、質の高いエダマメを育てることができます。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「エダマメの光合成」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから