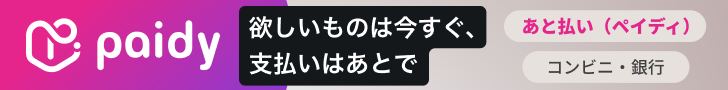栽培レシピ
-
今月の特集は【ゴーヤ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴーヤと水分管理のポイント ■ 基本特性 ゴーヤは乾燥には比較的強い一方で、過剰な湿気(加湿)には非常に弱い作物です。 ウリ科植物のため水分要求量は高め。 土壌に水が停滞するとカビが発生しやすくなるため、排水性の確保が必須条件です。 土壌は水がしっかり抜ける構造を意識して整えましょう。 ■ 育苗期(水分と苗づくり) **苗半作(良い苗が収穫の半分を決める)**といわれるほど重要な時期です。 育苗期は水分を多く必要とするため、乾燥させないように注意します。 灌水は午前中に行うのが原則。 玄米アミノ酸酵素液を500倍に希釈して与えることで、発芽が揃い、元気な苗が育ちます。 ■ 定植期(植え付けの注意点) 本葉3〜4枚のタイミングで定植 浅植えにすることがポイント 定植後は株元にしっかりと水を与え、乾燥を防ぐ 活着して生長点が動き出すまでの間は、水分をしっかり維持する この時期は、玄米アミノ酸酵素液を1000倍に希釈して灌水することで、根の活着と発育がスムーズに進みます ■ 親づる摘芯期(つる管理と水分) 本葉6〜7枚になったら、親づるを摘芯します 親づるを摘芯することで、子づるの生長が活発になります 子づるの伸長には、十分な水分と栄養が必要です 【子づるの生長を助ける管理】 玄米アミノ酸酵素液500倍希釈を使って、葉面散布を行います 散布は週2回を目安に 10アールあたり300L程度を使用 まとめ ゴーヤは、乾燥には比較的強いものの、加湿には非常にデリケートな作物です。育苗・定植・摘芯といった各ステージに応じて、適切な水分管理と玄米アミノ酸酵素液の活用を組み合わせることで、根張り・つるの伸長・果実の品質すべてに良い効果をもたらします。特に排水性のよい土づくりと、タイミングを逃さない水やりが、健全なゴーヤ栽培の鍵となります。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「ゴーヤの病虫害」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【ゴーヤ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴーヤ栽培における土壌と根の管理ポイント ■ ゴーヤの根の特徴 根は広く、深く張る性質を持っているため、土壌の乾燥や過剰な湿気(加湿)に敏感です。 そのため、排水性の良さが土づくりの基本条件になります。 同時に、保水力と保肥力(養分保持力)も重要です。 このような条件を整えれば、ゴーヤは非常に良く育つ作物です。 ■ 排水対策と土壌改善 明渠排水を整備して、大雨時の酸素欠乏を防ぎます。 過剰加湿は、生理障害や土壌病害の原因になります。 ハウス栽培の場合も、ハウス周囲に明渠を設けることが重要です。 【深耕の重要性】 ゴーヤは通気性・排水性を高めて酸素を供給することが、生育のカギです。 プラソイラによる深耕を行い、硬盤層・耕盤層をしっかり破壊することが大切です。 硬盤があると、根の伸長が妨げられ、生育不良になります。 一方、ロータリー耕だけでは耕土が浅く、排水性は不十分です。 ■ 土壌のpH管理 ゴーヤは酸性土壌に弱く、ややアルカリ性を好む作物です。 適正pHは6.0~7.0。可能であればpH7.0に近づけると理想的です。 ■ 乳酸菌もみがらぼかしの活用 基肥として10アールあたり500kgを投入 追肥は100kgを3~4回に分けて投入 もみがらぼかしに含まれるチッソ量は: 基肥:15kg 追肥:9~12kg このぼかしを使用することで、 土壌が団粒構造になり、微生物が活性化 土の持つ力(地力)が高まり、ゴーヤの健全な生育を助けます まとめ ゴーヤ栽培では、根の伸びやすさと排水性が決め手になります。「深く耕し、酸素を供給し、排水を良くする」ことで、病害を防ぎ、収量・品質ともに高めることができます。乳酸菌もみがらぼかしの活用と、適切なpH管理も忘れずに行いましょう。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「ゴーヤの水分の与え方」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツナの品質を高める光合成の活用法 光合成の基本植物は葉の光合成によって栄養を作り、生長しています。水と二酸化炭素(CO₂)から炭水化物を合成し、その栄養は生長の80%以上を支える重要な要素です。 光合成と葉の関係 植物が生長すると葉の枚数が増え、光合成量も増加 光合成量が増えるほど、生長速度も加速します 水分コントロールのポイント 根は構造が単純で、水分を調整する機能はありません 一方、葉は複雑な構造で、水分コントロール機能を備えています 光合成が活発にできる「良い葉」の条件 葉肉が厚く、色が淡い 大きく広がりすぎない チッソ過多でない葉 葉脈が立ち、産毛が多い(害虫の忌避効果も) 光合成を促進するための散布 玄米アミノ酸酵素液を500倍に希釈し、週2回、10アールあたり300~500Lを葉面散布 これにより、生長が早まるだけでなく、甘味も引き出されます 病害虫予防としての光合成活用 みどりの放線菌:病害予防 ニーム酵素液:害虫対策 病害虫が発生したときの対応だけでなく、予防として週1回の使用がおすすめ 光合成は「やりすぎ」にならない唯一の成長法 農業では多くのものが「過剰」で障害の原因になりますが、光合成に過剰害はありません 毎日行っても問題なく、回数が多いほど生長が早く、旨味も増します 実際には作業量の関係で散布回数を減らしているだけです 植物を元気に育てるには、光合成を最大限に活かす環境づくりが鍵です。葉の質を高め、玄米アミノ酸酵素液や微生物資材を活用することで、病気や害虫を防ぎながら、美味しく育てることができます。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。来月は「ゴーヤ」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツナに発生しやすい害虫とその対策 コマツナに付きやすい害虫 アブラ虫類 キスジノミハ虫 コナガ ナガメ モンシロチョウ ヨトウガ カブラハバチ ナモグリバエ ハクサイダニ コマツナ害虫の共通点 有機肥料の使いすぎ 化成肥料の使いすぎ 土壌の水分過多(過湿) 高温期のガス発生(肥料の分解による) 周囲に雑草が多い(害虫のすみかになる) 排水不良による酸素不足 害虫が発生しやすい時期 チッソが分解されやすい高温期 暑さが増す6〜8月頃や、残暑が厳しい時期 周囲の植物が少ない時期(特に山野が寂しい時) アブラ虫は気温25℃前後で最も活発に ヨトウ虫・ハエ・ガ類は高温期に増えやすい 9月(越冬前)は害虫が特に発生しやすい時期 害虫が付きやすい葉の特徴 チッソを多量に吸収した葉(チッソ特有の匂いが出る) 葉肉が薄く、大きく広がった形状 葉色が濃い緑色こうした葉は、光合成力や生長力が弱く根の張りも悪いため、害虫の標的になりやすい ※このような葉は、光合成力や生長力が弱く、根の張りも悪いため、害虫の被害を受けやすい。 害虫による被害 商品として出せない不良品の増加 生育が悪くなり、収量が減少 農薬・消毒剤の使用が増え、コストも上昇 害虫対策 害虫の発生には明確な原因があります。 → その原因を一つ一つ取り除くことが大切です。 過剰な肥料の使用(チッソ過多)を見直すことが重要です。 薬剤の使いすぎは土壌を酸性化させ、かえって収量を下げてしまうこともあります。...
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツナに発生しやすい病害と土壌対策 コマツナの主な病害 萎黄病 根コブ病 白さび病 炭疽病 軟腐病 べと病 リゾクトニア病 コマツナは作付け回数が多く連作になりやすいため、連作障害による病害が多く見られます。特に、萎黄病・根コブ病・白さび病は代表的な連作障害に起因する病気です。 生理障害の例 カルシウム欠乏症 ホウ酸欠乏症 これらは栄養バランスの乱れから起こるもので、見た目や生育に大きく影響します。 病害・連作障害の主な原因 肥料の残肥(分解しきれず土壌に残ったもの) 湿害(排水不良による過剰加湿) カビ菌の繁殖(カビは肥料をエサにして増殖) 肥料を多く入れすぎると、ガスが湧き、pHが低下する 作付け回数が多いほど、土壌の負担が増大し問題が深刻に 対策の基本は「土づくり」 定植前の土壌管理がすべての基本です。 カビの原因を排除し、土壌に酸素を十分に含ませることで病害の予防になります。 土壌の微生物性を高めることで、病気のリスクを下げ、健康な作物づくりにつながります。 また、光合成を重視した栽培管理を行うことが、病気予防にも有効です。 土壌病害の主な要因 土壌水分の過剰(過湿害) 肥料の過剰施用(土壌汚染) 耕盤層に蓄積した老廃物 植物が出す有機酸の蓄積 カビ系病害への具体的対策 みどりの放線菌200g+水100Lを目安に使用 玄米アミノ酸酵素液との併用で効果アップ 土壌病害が発生すると・・・ 生育不良、欠株、不良品の増加 収量が減り、収入に直接的な影響 有機肥料はカビ菌の原因になりやすく、化成肥料は土壌害虫のリスクを高める 土壌環境が悪化すると、翌年以降の栽培にも大きく影響し、連作障害の原因になる 土壌病害の予防には...