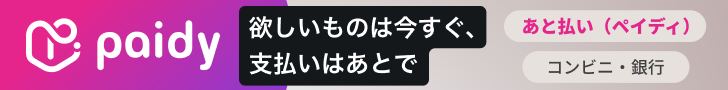栽培レシピ
-
今月の特集は【コマツナ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 コマツナ栽培における土壌管理と肥料のポイント コマツナ栽培の特徴 作付け回数が多く、残った肥料(残肥)が土壌に蓄積しやすい 浅根性のため、根が浅く、酸素を多く必要とする 生育には、排水性が良く、団粒構造が整った微生物豊富な土壌が最適 土壌環境が良いほど、根コブ病や萎黄病などの病害も少なくなる 稲作からの転作でも、土壌条件を整えれば問題なく栽培可能 排水が良く、適度に水持ちのある土壌が理想 肥料の使いすぎに注意 有機・化成肥料を多く投入しすぎると、土は徐々に硬くなり排水性や保水力が低下 年に何度も作付けをするため、そのたびに肥料や石灰を過剰投入しやすい 欠乏ではなく過剰症が原因で生育不良になることが多く、土壌の酸性化や病害発生にもつながる 明渠排水の整備 大雨対策として明渠排水は必須 土壌が雨で酸素不足にならないようにし、酸素を好むコマツナの健全な生育を支える プラソイラによる深耕 2~3回の深耕を推奨 土壌に酸素を含ませることで、残肥の分解が進み、根の伸びも良くなる 排水性・通気性を向上させるために非常に重要な作業 土壌のpHと吸肥力 適正pHは6.0〜6.5 pHが適正になることで微生物が活発に働き、吸肥力もアップ コマツナは後半の吸肥力が特に高いため、微生物とチッソの働きが生育に大きく貢献する 乳酸菌もみがらぼかしの活用 基肥として10アールあたり400kgを投入 チッソ量(基肥中)=約12kg 連続作付けするほど、土壌が団粒化し、微生物性が高まる その結果、病害も大きく減少し、健全な土壌環境が維持できる コマツナの栽培では、**「土づくりがすべて」**と言えるほど、事前の土壌管理が成果に直結します。適切な排水、pH、肥料のバランスを保ち、微生物の力を活かして、健康でおいしいコマツナを育てましょう。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「コマツナの病害」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【ゴボウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴボウの品質を高める光合成の活用法 光合成の基本と重要性植物は葉の光合成によって栄養をつくり、生長します。水と二酸化炭素(CO₂)を使って炭水化物を合成し、この栄養が生長の80%以上を支えます。光合成が活発になると糖度が上がり、品質の良い作物に仕上がります。 ゴボウの葉の生長期と光合成 ゴボウの葉の生長期は播種後70~100日 葉が多くなればなるほど、光合成量が増え、生長スピードも加速します 光合成がもっとも活発に行われるのは気温25℃前後です 水分コントロールのポイント 根は水分をコントロールできないシンプルな構造 一方、葉は複雑な構造で水分コントロール機能を持ち、環境に応じて調整が可能です ゴボウの旨味と光合成の関係 ゴボウは一般に「栄養生長が中心」と言われますが、それは根の強い吸肥力によるものです。しかし、光合成がしっかり行われることでアクが少なく、甘味のある上質なゴボウに育ちます。通常のゴボウとは違う、まろやかで新しい味わいが生まれます。 光合成が活発にできる「良い葉」の特徴 葉肉が厚く、色が淡い 大きく広がりすぎない チッソ過多でない葉 葉脈が立ち、産毛が多い(害虫の忌避効果も) 光合成を促進するための散布 玄米アミノ酸酵素液を500倍に希釈し、10アールあたり300Lを葉面散布 これにより、生長が早まり、ゴボウに甘味が出る 病害虫予防としての光合成活用 みどりの放線菌:病害予防 ニーム酵素液:害虫対策 トラブル時に対応し、予防的には週に1回の散布が理想的 光合成は「やりすぎ」がない栽培法 農業では「過多」が障害の原因になりますが、光合成には過剰による害はありません。 毎日行っても問題なし 作業の都合で回数を制限しているだけ 実施回数が多いほど、生長が早まり、旨味も増す 特に、ゴボウの茎や葉がよく育ち、高温が続くほど効果が表れやすいのが特徴です。光合成を意識した栽培管理で、甘くて質の良いゴボウづくりを目指しましょう。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。来月は「コマツナ」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから
-
今月の特集は【ゴボウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴボウに発生しやすい害虫と対策 ゴボウに付きやすい害虫 セン虫類 コガネ虫類 アブラ虫類(ウイルスを媒介するため特に注意) ヒョウタンゾウ虫 ヒメトガリノメイガ ゴボウハモグリバエ ピシュウム菌 ゾクトリア ゴボウ害虫の共通点 土壌の肥料過多による害虫発生 アブラ虫・セン虫・メイガ・ハモグリバエは特に肥料害と関連 水分過剰の環境でも発生しやすい 害虫が発生しやすい時期 6月後半~8月の高温期(チッソが分解しやすい時期) ゴボウの肥大期と重なるため、被害が深刻になりやすい アブラ虫はウイルスを媒介するため、発生を抑えることが重要 食害が出ると収量が大幅に減少 害虫が付きやすい葉の特徴 チッソを根から大量に吸収している(独特の香りがする) 葉肉が薄く、葉が大きく広がる 葉色が濃緑色をしている ※このような葉は、光合成力や生長力が弱く、根の張りも悪いため、害虫の被害を受けやすい。 害虫が寄りやすい原因 肥料過剰(特にチッソ過多) 水分過剰(湿害による根の異常吸収) 排水不良 害虫による被害 商品価値のない不良品が増える 生長が悪くなる 形状が崩れ、市場価値が低下 収量減に大きく影響し、A品の割合が減少 害虫対策 土壌のチッソ過多を防ぐことが最優先 過湿による根の異常吸収に注意する 特にゴボウは吸肥力が強いため、肥料管理を適切に行う 適切な土壌管理と排水対策を徹底し、害虫の発生を抑えることが、健康なゴボウの栽培につながります。 ...
-
今月の特集は【ゴボウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴボウの病害と土壌管理による対策 ゴボウに発生しやすい病害 ゴボウの病気は葉の病気と根の病気に分類されます。 葉の病気 モザイク病 うどん粉病 黒斑病 角斑病 黒斑細菌病 根の病気 紫紋萎凋病 萎凋病 根腐れ(やけ)病 そうか病 黒条病 黒あざ病 土壌病害の主な原因 過湿害(過剰な水分) 肥料過剰(土壌汚染) 耕盤層に蓄積した老廃物 植物から排出される有機酸の蓄積 ゴボウ病害の共通点 土壌の過湿・排水不良がカビ系病原菌の発生を促進 化学肥料や有機肥料の残留が腐敗し、病害の原因となる 病害が発生しやすい時期 7~9月の高温期(特にゴボウの肥大期) 高温多湿の条件で土壌水分が過剰になると発生しやすい 特にマルチフィルムを使用している場合、病害のリスクが高まる 土壌病害の対策 定植前の土壌づくりが最も重要 カビの発生要因を取り除き、土壌内の酸素量を確保することが病害予防の鍵 土壌病害が発生すると・・・ 生育不良・欠株・不良品の増加 収量が減少し、収益に直結する 有機肥料はカビ由来の病害を引き起こしやすく、化成肥料は土壌害虫を発生させやすい 翌年の栽培にも影響を及ぼし、連作障害の原因となる 土壌病害を予防する「乳酸菌もみがらぼかし」 土壌病害のリスクが高い場合は、醗酵ニームケイクを20%混合し、乳酸菌もみがらぼかしを作成する 微生物の力で土壌を浄化し、病害の発生を抑える...
-
今月の特集は【ゴボウ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴボウの栽培に適したほ場選定と土壌管理 ほ場選定のポイント 排水性の良い土壌を選ぶゴボウは滞水に弱いため、通気性と排水性が重要。 作土層が深いことが必要ゴボウの根が深く伸びるため、深耕が不可欠。 明渠排水を整備し、大雨対策を行う 雨による酸素欠乏を防ぐため カビの発生防止にもつながる ゴボウの作土層が深いため、深めに明渠を掘ることが重要 土層の深さ 70~80cm(トレンチャー耕) 酸素量を確保するため深耕する 柔らかい作土層を作ることが大切 排水が悪いと良いゴボウは収穫できない 1m以上深く耕すと直根が伸びすぎるため注意 土壌のpH管理 適正pH:6.0~7.0(6.5以上が理想) 酸性に弱いため、特に火山灰土ではpH管理が重要 畝の設計 畝高:15~20cm 株間:5~6cm 畝間:66~72cm 早出し栽培 → 株間を広めに取る 遅出し栽培 → 株間を狭めにする 乳酸菌もみがらぼかしの投入量 基肥:10アールあたり600kg 追肥:100kg×2~3回 10アールあたりのチッソ量 基肥:9kg 追肥:6~9kg 前作の影響がある場合、基肥の前に改良剤を投入(10アールあたり300kg) ゴボウは多肥を好まないため、適量を守る 乳酸菌もみがらぼかしの投入方法 0~30cmに300kg 30cm以下に300kg 2層に分けて投入することで土壌のバランスを整える...